PR
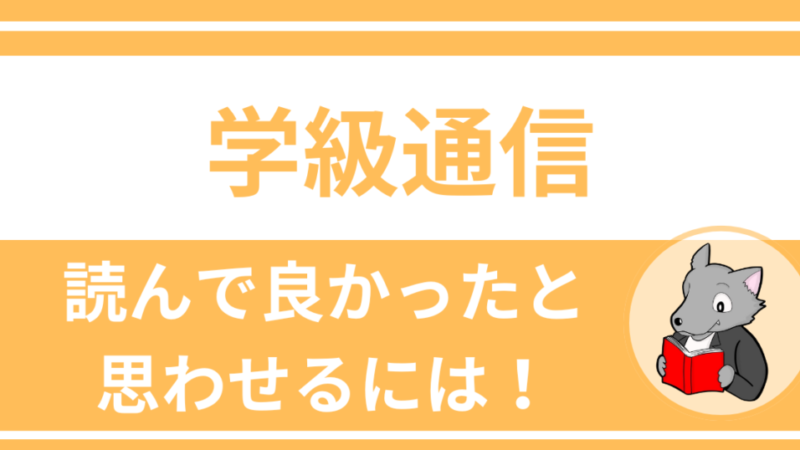
「学級通信、なんだかつまらないな」
「もっと子どもや保護者の心にひびく通信をつくりたい」
と、なやんだことはないでしょうか。
じつは、多くの先生が学級通信の作成で、にている悩みを持っています。
この記事では、学級通信がつまらなくなりがちな理由と、それを解決するための3つの視点をお伝えします。
結論からいうと、学級通信は「読ませたい人」にしっかり届く内容にすることが大切なのです。
なぜ学級通信が「つまらない」と感じられるのか?

なぜ、せっかく書いた学級通信がつまらないと感じられてしまうのでしょうか。その理由をくわしく見ていきましょう。
- 全員向けの文章は誰にも刺さらない
- 「できる子」こそ、読む価値のある学級通信を求めている
全員向けの文章は誰にも刺さらない
みんなにわかるように書こうとすると、あたりさわりのない内容になりがちです。その結果、だれの心にも響かない文章になってしまうのです。
当たり前のことばかり書いても、読者は「知ってるよ」と感じるだけでしょう。
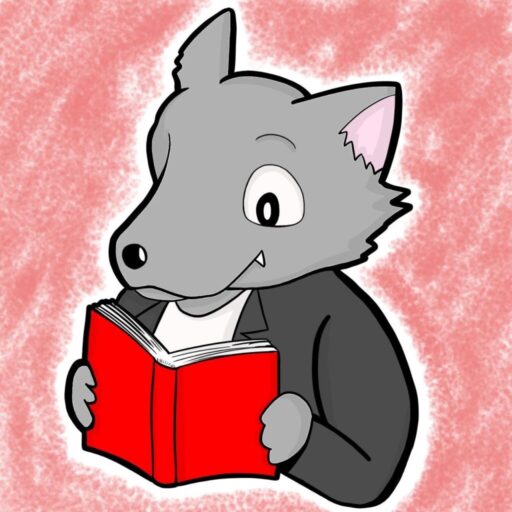
「良い天気ですね!」「そろそろ進級ですね!」「思いやりを持ちましょう!」
「夏休みは気を付けて!」「人を傷つけてはいけません!」

毎日、同じ内容だし、言われなくてもわかってるよ!
「できる子」こそ読む価値のある学級通信を求めている
そもそも学級通信とは誰が読むのでしょうか?
よくある勘違いが、学級通信を通じて思いやりを持ってもらおうとするやり方です。
しかし、学級通信という文字で書かれている段階で、クラスの中でも読める人は限られてきます。学級通信を真面目に読む人はすでに思いやりを持っている場合が多いのです!
だからこそ、学級通信というのは、読んでいるターゲットを「クラス全員」からもう少し絞る必要があります。
つまらない学級通信から脱却する3つの視点

では、どうすればつまらない学級通信から抜け出せるのでしょうか。ここでは、3つの具体的な視点をごしょうかいします。
- ①「誰か一人」に向けて書く
- ②「慣れ」や「一歩踏み出す勇気」といった共感できるテーマを選ぶ
- ③上位層が「面白い」と感じる内容が口コミを生む
①「誰か一人」に向けて書く
全員に届けようとするのではなく、特定のだれか一人に向けて書いてみましょう。たとえば、最近がんばっている〇〇さんや、なやみをかかえていそうな△△くんを思い浮かべます。
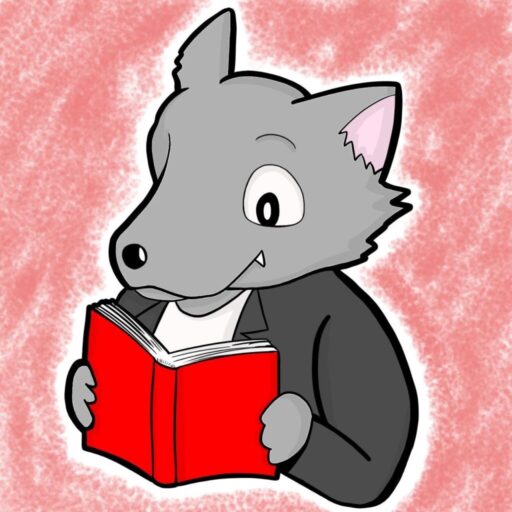
1人を奮い立たせるような文章が、同じような境遇の人にも当てはまり、結果的にいろんな人を奮い立たせる内容になります!
②共感できるテーマを選ぶ
子どもたちが共感しやすいテーマを選ぶことも大切です。
共感しやすいテーマ例:
- 失敗してもまた挑戦することの大切さ
- 友だちと協力して得られる刺激
- 努力が報われるときの要員
など、具体的なエピソードとともに、その生徒が普段から受け取らないニッチな内容が深く心に刺さります。
③上位層が「面白い」と感じる内容が口コミを生む
少しむずかしい内容や、考えさせられるテーマも取り入れてみましょう。
意欲の高い子どもたちが「おもしろい!」と感じれば、それが口コミで広がることがあります。
「先生の学級通信、〇〇って書いてあったよ」という会話が生まれるかもしれません。
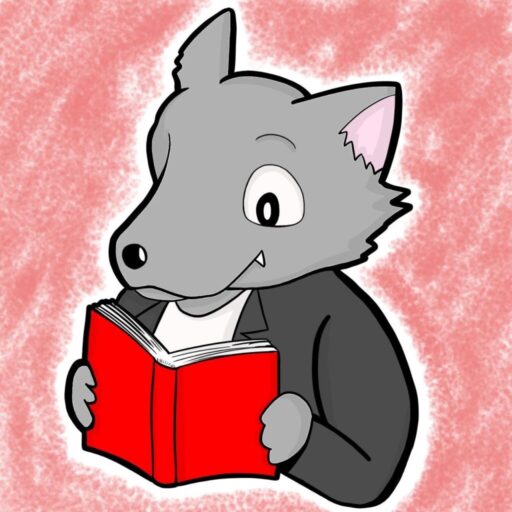
「giveする人が得をする」という話とか評判がよかったです!
結論:学級通信は「読ませたい人」に届く内容であるべき

最後に、学級通信のあるべき姿についてまとめます。たいせつなのは、届けたい相手にしっかり届けることです。
- 読める層に向けた高品質な文章が学級全体を動かす
- AI活用は「良質な例文」を持ってから
読める層に向けた高品質な文章が学級全体を動かす
まずは、しっかりと内容を理解できる層に向けて、質の高い文章を書きましょう。
彼らが内容を理解し、共感してくれることが大切です。その反応が、クラス全体のよいふんいきをつくるきっかけになります。
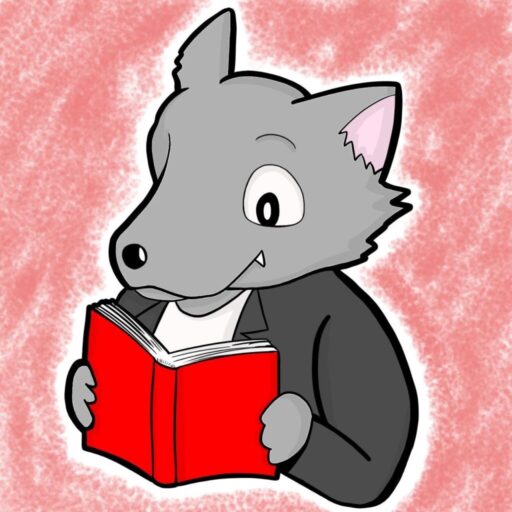
学級通信で、思いやりの大切さを説いて以降、特に話したこともない生徒の思いやりが出てきたことがあります!
AI活用は「良質な例文」を持ってから
最近、話題のAIは、文章作成の助けになります。
しかし、AIをうまく使うためには、まず自分の中に「よい文章」の基準を持つことが必要です。
どのような文章が子どもたちの心に響くのか、試行錯誤してみましょう。そのうえでAIを活用すれば、より効果的な学級通信が作れるはずです。
| AI活用のメリット | AI活用の注意点 |
|---|---|
| 時間を短縮できる | よい例文がないと効果がうすい |
| アイデア出しのヒントになる | 最終的な判断は自分でおこなう |
| 文章のたたき台をつくれる | 個性や熱意が伝わりにくい場合も |
この記事でお伝えした視点を参考に、ぜひあなたの学級通信をより魅力的なものにしてください。