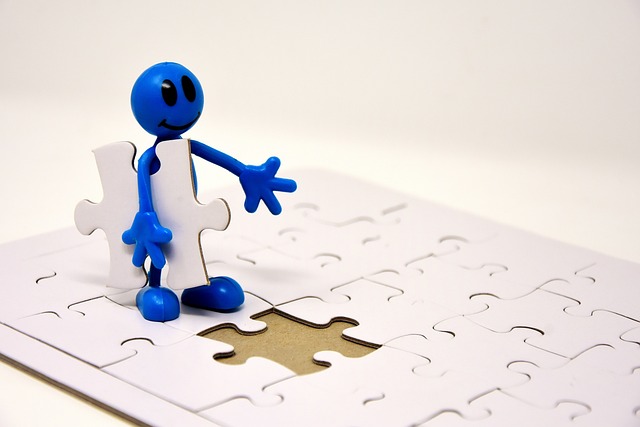PR
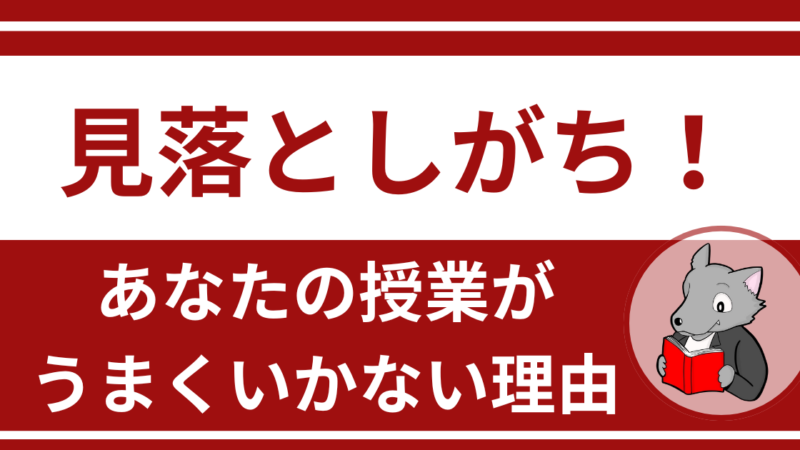
授業を作るとき、こんな悩みはありませんか?
- 「教材研究はしているのに、授業がイマイチ盛り上がらない…」
- 「授業後に、生徒にどんな力がついたか自信が持てない…」
- 「授業の目的を意識できていない気がする…」
授業の設計において、つい忘れがちなのが「生徒にどうなってほしいか」という視点です。
この視点が抜けると、授業が単なる知識の詰め込みになり、生徒の主体的な学びにはつながりません。
この記事では、授業づくりにおける「生徒にどうなってほしいか」を設定する重要性と、その具体的な考え方について解説します。
授業づくりで忘れがちな視点とは?
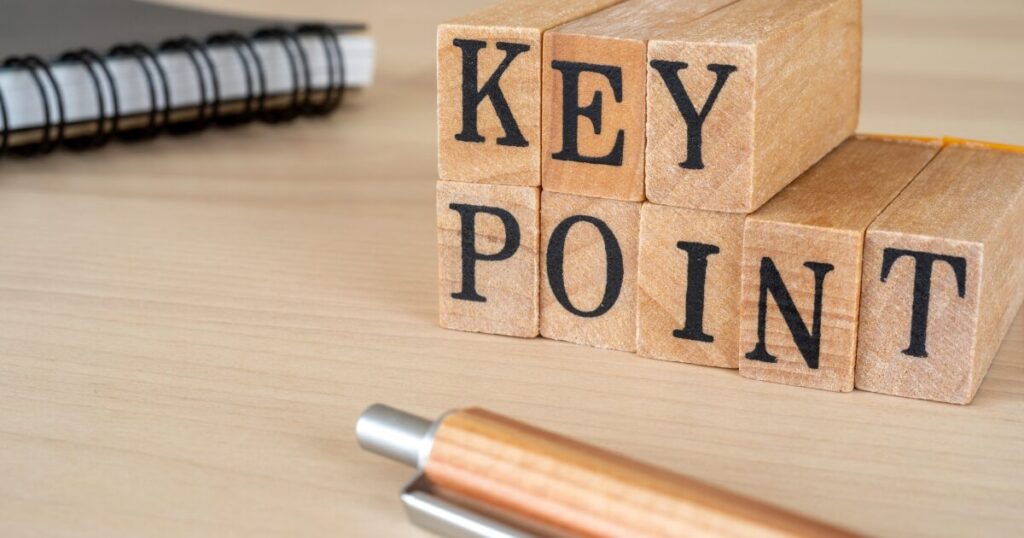
授業を作る際に忘れがちな重要ポイントについて解説していきます。以下の2つのポイントを中心に見ていきましょう。
- 生徒に「どうなってほしいか」を考えない授業のリスク
- 教科が好きなだけでは足りない理由
生徒に「どうなってほしいか」を考えない授業のリスク
生徒の成長イメージを持たない授業は、効果が半減します。目指す姿がなければ、生徒も何を意識して学べばいいかわからず、受け身になりやすいからです。
例えば、職員会議や外部研修を受けたとき、「この時間、何のためにあるのか」がわからないと眠くなるのと同じです。生徒も授業の意味がわからなければ、主体的な学びにはつながりません。
だからこそ、授業ごとに「この授業を通して生徒がどう成長するか」を明確に設定することが重要です。
「教科が好き」だけでは足りない理由
教員が自分の教科を好きな気持ちだけでは、生徒の学びを引き出すことはできません。教師自身の情熱だけでは、生徒にとっての学びの意義が見えないからです。
| 教師視点 | 生徒視点 |
|---|---|
| 理科が楽しい! | これって何の役に立つの? |
| 歴史が面白い! | 今の自分に関係ある? |
教科を通して、「生徒にどうなってほしいのか?」というエゴが、授業には必要なんです!
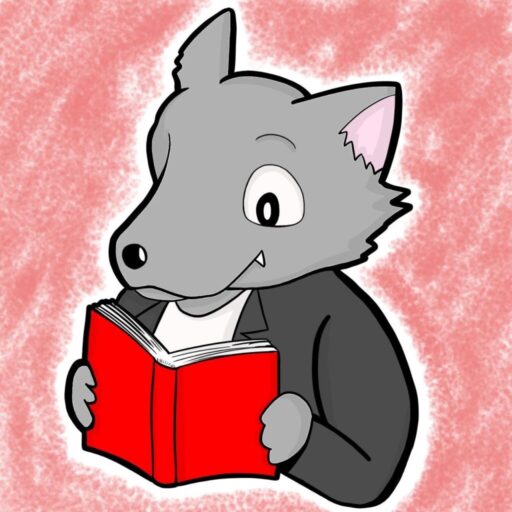
もちろん、教員が勉強に情熱を持っていることは、めちゃくちゃ大事です!
生徒にどうなってほしいかを設定する重要性

生徒にどうなってほしいかを設定する重要性について、次の2つの視点から解説します。
- 短期的な目標と長期的な目標を設定する
- 教科内容と生徒の未来をつなげる工夫
短期的な目標と長期的な目標を設定する
目先の成果と将来の成長、両方を見据えた目標設定が不可欠です。短期で成果を感じられるとモチベーションが上がり、長期で成長を感じることで継続的な学びにつながります。
| 短期目標例 | ・他の人に褒められる ・ニュースがわかるようになり、モテる ・仕事ができる人と思ってもらえてかっこいい |
| 長期目標例 | ・世界を俯瞰して見れる ・教養が身につく |
これらを授業の最初に明示することで、生徒の学びへの姿勢が変わります。
教科内容と生徒の過去・現在・未来をつなげる工夫
教科内容を生徒の現在・未来に直結させることで、学びの意味を感じさせられます。生徒は現在・未来に役立つと感じたとき、学びへの意欲が高まります。
例えば、室町時代の村社会の勉強を通して「共同体で助け合う意識」を学び、現代のコロナ禍の問題に応用して考える力を育めます。
教員が、現代においてどのように思考しているのかを模範として見せることで、生徒にも「こんな風に学べばいいのか!」と気付きを与えられます。
授業づくりに役立つ考え方とアプローチ

授業づくりに役立つ考え方とアプローチについて、次の2つの観点から紹介します。
- 教材研究は「伝えたいこと」を見つけるためにある
- 授業手法は目的達成の手段にすぎない
教材研究は「伝えたいこと」を見つけるためにある
教材研究は、教科書の解説ではなく、自分が生徒に届けたいメッセージを探す作業です。自分の思いが込もった授業は、生徒の心に届きやすくなります。
- 教科書の内容を機械的に伝えるのではなく、「これが現代にどう生きるのか」を意識して解説する
- 生徒がこれを学ぶことで、どんなメリットが得られるのかを意識する
自分の言葉で語れる授業を目指しましょう。
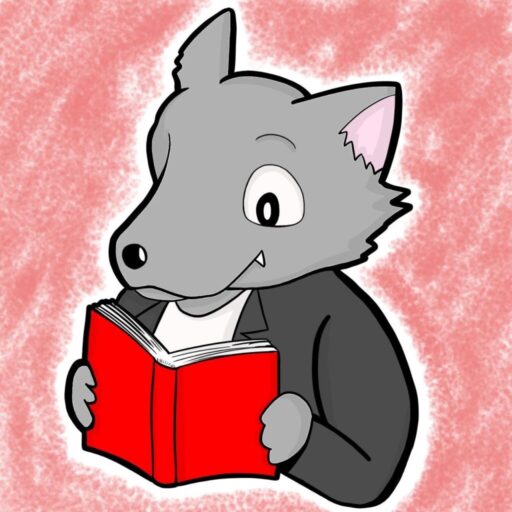
本来の塾の月謝から考えると、1つの授業には、もっと価値があるはずなんです!
授業手法は目的達成の手段にすぎない
グループワークやアクティブラーニングも、あくまで目的達成のための手段です。手法に振り回されると、肝心の「何のための授業か」が見えなくなってしまいます。
ディスカッションを取り入れるなら、「自分と異なる意見を受け入れる力を育む」など、明確な意図を持って行いましょう。
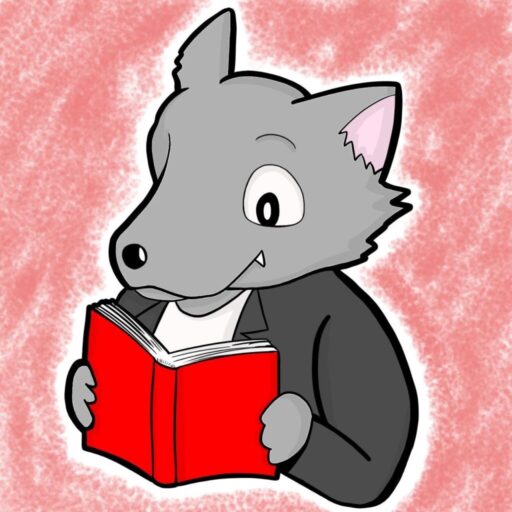
最近は、「授業を聞いてくれないから」「流行だから」という理由でアクティブ・ラーニングしている人が多すぎます!
手段ではなく目的を軸に、授業をデザインする意識を持つことが大切です。
まとめ
この記事では、授業づくりで忘れがちな視点とその対策についてご紹介しました。
- 生徒に「どうなってほしいか」を明確にすることが授業の質を高める
- 教科の好き嫌いに関係なく、未来を意識した授業設計が重要
- 短期と長期の目標を設定することで、生徒の学びの方向性が定まる
- 教材研究は単なる準備ではなく、伝えたいメッセージを見つけるための大切な作業
- 手法にとらわれず、目的から逆算して授業を設計することが鍵
授業づくりに悩んだときは、「この授業で生徒にどんな未来を見せたいか」を考えるところから始めてみましょう。小さな工夫の積み重ねが、生徒たちの大きな成長につながります。あなたの授業が、子どもたちの未来を切り拓く力になることを願っています!